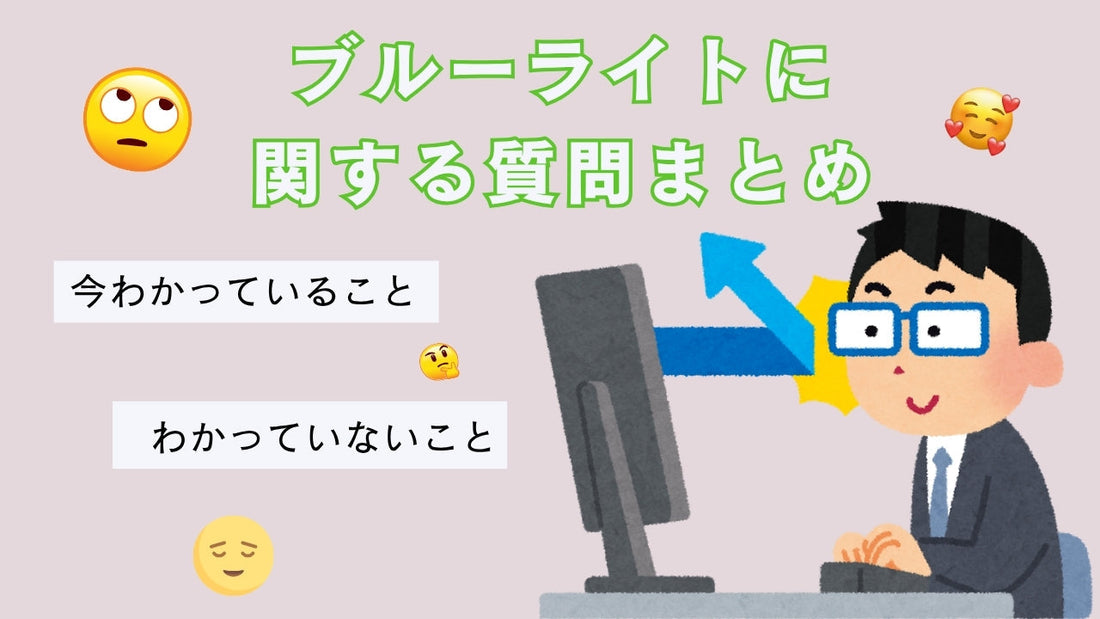
ブルーライトカット眼鏡の登場から考える“青い光”の誤解と背景について紹介します
共有
2025年EDIX大阪展示会の企画として、ブルーライトについて調べたことをまとめたため今回紹介します。今回の内容は、わかりやすさを目的としていること、医療に関する内容も含まれるため、リンク先やご自身でも確認していただくようお願いします。
最初に:ブルーライトカット眼鏡の普及の歴史
ブルーライトの話を始める上で必要になるのは、この単語はどこから始まったのかという点です。この中でも大きいのはスマートフォンの普及とブルーライトカット眼鏡の登場ではないでしょうか。さらにここで注目したいのは2021年からの「過剰広告への指摘」です。
| 年代 | 出来事・技術進化 | 内容 |
|---|---|---|
| 2000年代 | 液晶ディスプレイの普及 | パソコン・テレビの長時間使用が一般化。ブルーライトの影響が注目され始める。 |
| 2010年前後 | スマートフォン普及 | 就寝前の使用などで、目や睡眠への影響が話題に。 |
| 2011年 | 眼鏡大ヒット | ブルーライトカット眼鏡が商品として大ヒット。大手メーカーが参入。 |
| 2010年代中盤 | 一般化 | 子ども用・オフィス用など多様なラインナップが登場。 |
| 2020年以降 | テレワーク・オンライン授業 | 利用者が再び増加。家庭・職場に定着。 |
| 2021年~ | 過剰広告への指摘 | 消費者庁が「科学的根拠に乏しい」表現に注意喚起。現在は「目の疲労軽減」など控えめな表現が主流。 |
2021年に起きたこと:日本眼科医会のブルーライトカット眼鏡に関する意見
公益社団法人日本眼科医会が、2021年4月14日に発表した「小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見」です。この内容によると、ブルーライトカット眼鏡は科学的な根拠が乏しく、効果も証明されていないとのことでした。以下は要約です。
- ブルーライトは太陽光や液晶画面に含まれる可視光線の一部。
- 小児へのブルーライトカット眼鏡使用には科学的根拠が乏しい。
- 液晶画面の光は自然光より弱く、網膜への害はない。
- 太陽光は近視予防など小児の発育に重要。
- 眼精疲労への効果は証明されていない。
- 就寝前以外の使用は体内時計への効果も不明。
- 日中は明るい環境で過ごすことが推奨される。
- 小児にブルーライトカット眼鏡を使う必要はない。
なぜこれまでブルーライトが悪者になったのか?
これはLEDの進化と、バックライトにLEDを採用したディスプレイやスマートフォンとの関係が原因ではないでしょうか。
LEDの進化と普及の歴史
下の表はLEDの進化についての年表となります。ここで注目すべきは青色LEDが開発された1993年です。青色LEDの実現により、赤・緑・青の光の三原色がそろいました。これにより混ぜれば明るくなる加法混色(赤+緑+青=白)により背景となる白を作り出すことに成功したのです。
| 年代 | 出来事・技術進化 | 内容 |
|---|---|---|
| ~1980年代 | 赤・緑LEDが実用化済 | 主に表示ランプに使用。 |
| 1993年 | 青色LEDの実用化 | 赤﨑勇氏らが開発。白色LEDの基礎となる。 |
|
2000年代前半 |
高輝度白色LEDの登場 | 明るさ・コストが実用レベルに。 |
| 2007年頃 | LED電球の市販開始 | 家庭用として販売され始めるが、まだ高価。 |
| 2010年前後 | 普及加速 | 価格が下がり、政府の省エネ推進政策も後押し。 |
| 2010年代 | 社会全体でLED化 | 街灯、家電、車、照明の多くがLED化。 |
ただ、LEDで白を得るために、理論上は「赤・緑・青のLEDを組み合わせる方法(RGB合成)」で行えますが、コストの関係で「青色LED1個+黄色蛍光体(ちなみに光の赤と緑を混ぜると黄色)=白」という組み合わせになりました。1個の青色LEDチップと蛍光体層だけで白色を出力できるため、設計もコンパクトになるとのことです。
LEDの発光原理・構造と仕組み - マイクラフト
ただ、青色のLEDチップを使うようになった結果、LEDのライトは自然太陽光と比較して、白を表示させるときでも青の成分が強く出ることになりました。これはメインとして青色LEDを使っているため当然と言えば当然です。上の図で言えば、450~500nmの波長の部分となります。
ただこのぴょこんと飛び出た青色成分の分光特性によって「ブルーライトを抑えれば目が疲れにくくなるのでは。」という考えが生まれてきたのではないでしょうか。
さらに話がややこしくなるブルーライトの害について
ブルーライトの害について調べてみると、代表的な論文として、ブルーライトを含む短波長の光でアカゲザルの網膜が損傷するという論文がありました。
網膜への損傷リスクに関する研究(Hamら, 1976年)
- 論文タイトル:Retinal sensitivity to damage from short wavelength light
- 著者:W.T. Ham Jr., H.A. Mueller, D.H. Sliney
- 掲載誌:Nature, 1976年3月11日, 260(5547):153-5
- DOI:10.1038/260153a0
- PubMedリンク:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/815821/
読んでいるだけで目が痛くなる実験内容
Hamという科学者が行ったこの実験では、アカゲザルの網膜に、短い波長の光=青っぽい光や紫外線に近い光を当てて、どのくらいの強さで目が傷つくのかを調べたそうです。
その結果、青色光には他の光と比べて網膜を傷つける力が大きいことがわかりました。特に、人の目には見えにくい紫外線に近い光では、もっと強いダメージが起こるとのことです。
この研究がきっかけで、「ブルーライトって、もしかして目に悪いんじゃない?」という考えが出てくるようになったとのことでした。この論文はブルーライトの安全性についての研究や対策の出発点となります。また、ブルーライトは他の波長の光と比べても関心が高く論文数も多いとのことでした。
ただこの実験を具体的に調べると、日常生活のブルーライトとは大きく異なり、2500Wのキセノンランプを水晶体を取り除いた眼に直接当てていました。

Ham論文の条件下で用いられた2500Wキセノンランプの強度は、スマホの100,000倍以上の明るさとなります。映画上映やイベントなどで使用する業務用プロジェクタレベルとのことです。
条件があまりに違いすぎるため、スマホのブルーライト=網膜損傷リスクが高いという主張はできないと言えるでしょう。
日本眼科医学会の「科学的根拠が乏しい。」というのも上記のような結果をふまえて述べられているのではないかと思われます。
眼鏡業界においてもブルーライトカット眼鏡については正しく啓発しています
こちらは眼鏡大手のHPになりますが、2021年4月28日の段階において、ブルーライトカット眼鏡について正しく啓発しています。また、夜間に光を浴びると体内時計が乱れる点は有力な証拠が集まっています。
ブルーライトカットメガネ・レンズをお使いいただくにあたって(株式会社JINSホールディングス)
ただCMも含めてブルーライトカット眼鏡の有効性が主張された期間はかなり長いものでした。そのため多くの人の意識の中にはブルーライトが問題であると残り続けているのかもしれません。
仕事で出会う人の中にも、ブルーライトカット眼鏡を使用されている方がおられます。ただ中々伝えにくい内容でもあるため、次に眼鏡を買い替える時には参考にしてもらえると嬉しいです。
弊社製品に対するブルーライトに関する質問への答え
電子ペーパーは表示特性上、ライトをオフにしても表示が可能です。そのため、お客様からの「ブルーライトをオフにできるのですか?」という質問に対しては、「ブルーライトも含めて光源から直接発生するライトを完全にオフにできます。」とお答えしています。
ただ、「ブルーライトが眼精疲労の原因ではないとすると、眼精疲労の原因は何ですか?」と聞かれると、以下の三点で説明しています。
- まばたきの回数が減少するため目が乾きやすくなる
- 強い光を見ていると毛様体筋が緊張し続けることになるため疲れが蓄積する
- 調光により光のちらつき(フリッカー)が発生している
スタッフ個人的な意見として
2については周囲の環境とモニターの光を合わせるのは難しいこと、また高精細なディスプレイになるほど、光を強く出さないと見えにくいため、この調整で筋肉が疲れるのではないかと思っています。
3については、最近のデスクトップモニターはフリッカーの発生しにくいDC調光の製品が増えてきたため解消されつつあるかもしれませんが、ノートパソコンではPWM調光が主流です。過去に複数台の液晶モニタやノートパソコンを検証しましたが、フリッカーの発生する液晶は確かに目が疲れます。
補足として厳密な話をすると、太陽や蛍光灯などの光にはブルーライト成分が含まれています。光が無いと物が見えないため、完全にカットというのはできません。ただ、光源を直接見つめなくてもよいことは電子ペーパーの利点だと思います。
最後に宣伝:大阪のショールームでご覧いただけます
弊社は、紙のように自然光でご覧いただける電子ペーパータブレットや電子ペーパーモニターを販売しております。目に優しいため、長時間のPC作業や読書、在宅勤務にも最適です。プログラミングを行う会社等であれば、従業員様の福利厚生目的としてもおすすめです。

DASUNG253シリーズ 25.3インチ 電子ペーパー モニター ディスプレイ – SKTNETSHOP
大阪のショールームでは実機をご覧いただけますので、ぜひ一度その見やすさと快適さをご体感ください。法人様向けに導入相談も承っております。
https://sktgroup.co.jp/dasung-paperlike-color/
関西ICT教育展に出展予定です
8月7~8日にインテックス大阪で開催されるICT教育展にも出店予定です。電子ペーパーを用いたタブレットやモニターに興味のある方はぜひお立ち寄りください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

